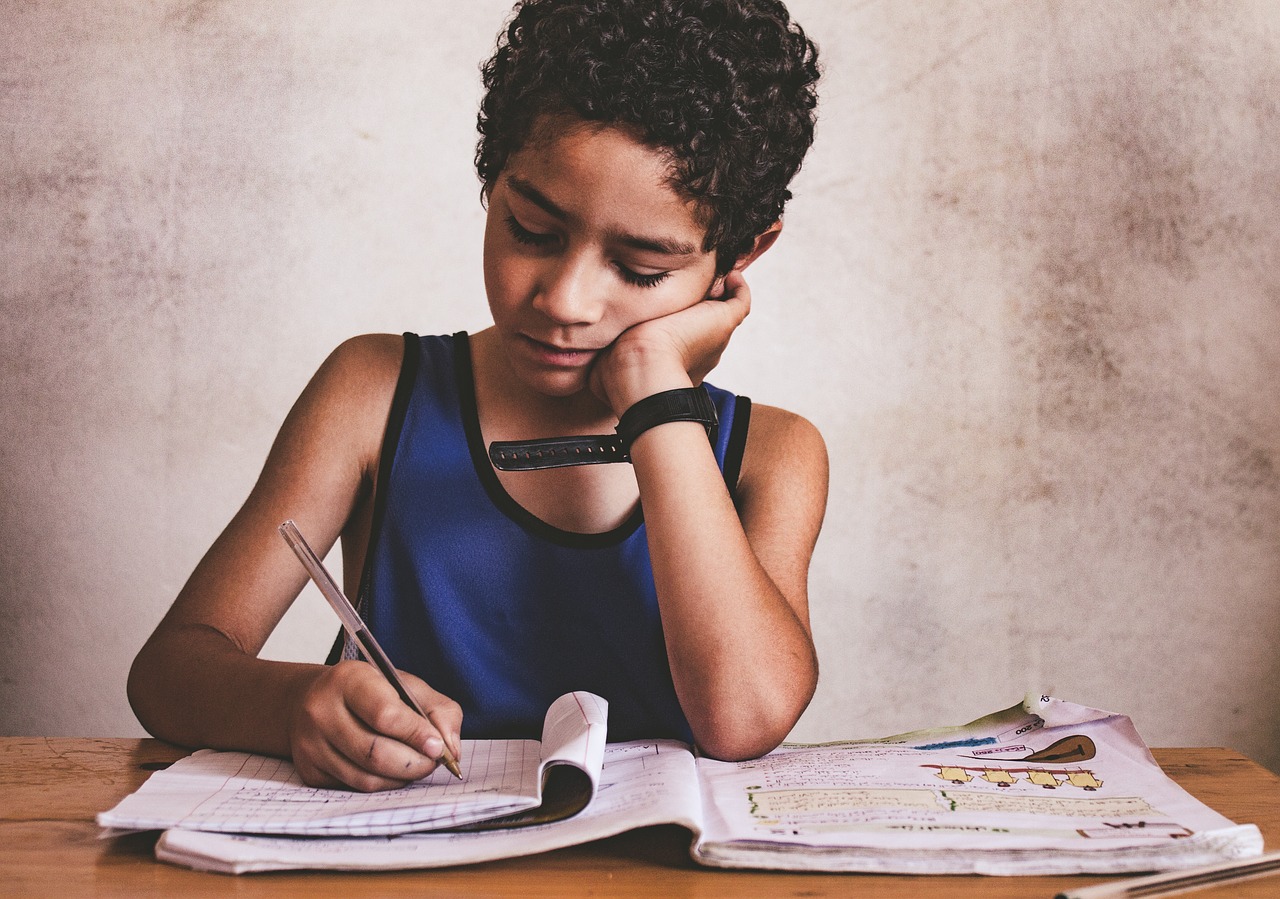
目次
1.UNICEFの活動を理解する
UNICEF(ユニセフ)の正式名称は、国際連合児童基金(United Nation’s Childrens Fund)と言い、1946年に国際連合総会の補助機関として設立されました。
国際連合には3つの活動目的がありますが、ユニセフはその内の一つである「経済的・社会的・文化的・人道的な国際問題の解決のため、および人権・基本的自由の助長のための国際協力」の達成が設立の目的としています。
設立当初は、国際連合国際児童緊急基金という名称で、第二次世界大戦後の緊急援助のうち子どもを対象にした活動を行っていました。
日本も1949年から1964年にかけて、脱脂粉乳や医薬品、原綿などの援助を受けていました。
第二次世界大戦後の生活にあえいでいた当時の日本も主要な被援助国の一つでした。脱脂粉乳を水でといたミルクは子どもたちの学校給食のメニューにもなりました。
第二次世界大戦後の混乱が落ち着き、緊急援助が行き渡るのにつれて、ユニセフの活動範囲は広がり、開発途上国や戦争・内線で被害を受けている国の子どもへの支援を活動の中心としているほか、「子どもの権利条約」の普及活動にも務めています。
2.親に対する栄養知識の普及や教育活動への支援にも注力している
かつては、物資の援助活動が中心ですが、特に開発途上国においては、生活の自立がなければ子どもの状況は変わらないという認識になり、親に対する栄養知識の普及や子どもたちの教育活動への支援にも力を入れてきています。
特に開発途上国や紛争による難民の子どもたちには、水や診察所などの衛生施設などの基礎サービスの再建や学校の再開など、将来その国を担う子どもたちが健康で自立できるような支援が柱になりました。
また予防接種や医薬品の提供などを通じて不十分な医療体制を補い、多くの子どもたちの生命を救っています。
開発途上国だけでなく、先進国においても深刻な自然災害が起きたときの支援活動も行っています。
2011年に起きた東日本大震災でもユニセフの支援活動が行われました。
1965年には、国際援助機関としての活動が認められて、ノーベル平和賞を受賞しました。
3.本部はニューヨークだがユニセフ現地事務所が活発に活動している
ユニセフの本部はニューヨークに置かれていますが、実際の活動については、開発途上国におかれて実際の支援に当たる「現地事務所」、世界の7つの地域に分けて分担する「地域事務所」が行っています。
その他にも先進国に存在してUNICEFを支える国内委員会があります。
この国内委員会は、協力協定を結んでユニセフ本体を支え民間団体(NGO)であり、ユニセフ内の組織ではありません。
国内委員会は民間からの支援を募り、各国内でとりまとめた支援をユニセフ本体におくり、開発途上国におけるユニセフの活動を支えています。
この民間からの支援を受けながら活動をする点もユニセフ独自の方法です。
・・・日本ユニセフ協会について
特に活発に活動しているのがユニセフ現地事務所です。
155の国と地域に置かれて国際職員と国内職員で構成されています。
現地の状況を調査し、国や地域別の援助計画や予算を立案し、計画にしたがって援助を実施します。
実施後は、モニタリングを行い、その評価をして次の支援活動へとつないでいきます。
先進国から開発途上国への援助というだけでなく、開発途上国が自立していけるような学校教育、職業訓練などを進めるとともに将来を担う地域のリーダーを当事者の間から育てていくという方針が貫かれています。
4.必要な費用の確保が大きな課題
このように多くの国々で子どもを中心に生活支援や教育活動の支援を行い、特に被災者や難民、開発途上国の人たちを支えているユニセフですが、いくつかの課題があります。
最も大きな課題は必要な費用の確保です。
国際連動も加盟国の分担金で支えられていますが、十分ではなく活動に支障が出るのではないかという危惧があります。
ユニセフも政府機関からの資金が約60%にとどまり、民間団体である各国の国内委員会からの資金が30%と大きな割合で、民間からの寄付等による収入が大きな部分を占めています。
ユニセフ自身の財源が限られている中で、民間からの善意の寄付に頼る部分は貴重ですが、世界経済の影響を大きく受ける部分でもあり、安定した資金の確保は大きな課題です。
5.活動を行う職員の健康や安全の確保
もう一つの課題は活動を行う職員の健康や安全の確保です。
ユニセフの現地事務所が置かれる地域には、開発途上国や被災地、紛争による難民キャンプなど過酷な環境に置かれている地域が多くあります。
これらの場所で健康に毎日の活動を行うためには、継続した支援活動を行えるだけの職員に対する医療支援や健康確保の支えが欠かせません。
直接支援にあたる職員だけでなく、その職員を支援する態勢が必要です。
まして、紛争地域においては、戦闘行為が行われている場所から近い距離で活動することもあり、生命や大きな怪我の危険と隣り合わせになることも少なくありません。
テロ活動の標的になり犠牲になった職員もいます。
国際連合の活動である平和維持活動との連携なども含め、職員の安全を確保する必要性が高まっています。
最終更新日 2025年6月27日 by uyhom











