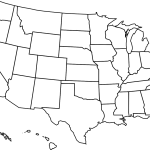「兜飾りの由来を知りたい」
「兜飾りの購入のポイントを知りたい」
「兜飾りはどうやって選べばいい?」
兜飾りは端午の節句の五月人形の一種で、男子の誕生をお祝いしたり、成長や健康を祈って飾るものです。
五月人形には室内の内飾りと屋外の外飾りがありますが、現代では鎧兜の内飾りが主流となっています。
また外飾りといえば鯉のぼりですが、かつては武者のぼりも立身出世の象徴として用いられてきました。
兜に込められた意味は鎧と同じく、男の子を病気や事故による怪我などから守り、武士のように強く育って欲しいという願いに基づきます。
コンパクトな兜飾りも登場している
核家族化が当たり前になった現在は、鎧兜を一式飾るのが難しく、飾らないという家も少なくないです。
そこで、時代の変化とニーズに応える形で、コンパクトな兜飾りも登場しています。
中には棚において置けるサイズの商品もありますし、使わない時に収納しておけるタイプも存在します。
兜は見るからに立派なデザインですが、実は各部に名称があります。
頭の部分を鉢と呼びますが、後頭部はをしころで前面の両側を吹返しといいます。
印象的な角は鍬形、前面のひさしにあたる部分は眉庇という名前です。
結紐は忍緒といいますから、実に細かく分けられていることが分かります。
全てを覚えるのは簡単ではありませんが、知っていると物知りに思われるので、博識になりたい人は覚えることをおすすめします。
鉢の部分は兜によってデザインが異なり、合わせ鉢と呼ばれる複数枚の鉄板を接ぎ合わせて作られたものもあります。
吹返しは本来、刀から顔を守る為のものですが、兜飾りでは兜を美しく見せる為にデザインに工夫が凝らされます。
鍬形はクワイの葉に由来する名称
鍬形はクワイの葉に由来する名称で、形が似ていることから名づけられました。
忍緒は言うまでもなく兜を頭に固定する紐で、無双結びや総角結びなど様々な結び方があります。
他にも、竜の形をしている装飾の竜頭、兜の芯となる芯木、芯木を隠す家紋や名前が入っている袱紗に分けられます。
櫃は兜を収納したり飾る際に使用する専用の箱で、脚がついているタイプもあります。
兜は昔であれば格式が高い床の間が定番でしたが、現代の住宅では特に決まりはなく、目につきやすいリビングにも飾ることが可能です。
そもそも五月人形は子供の為のものですし、兜は男の子の健康や成長を祈って飾るわけですから、子供の目につく場所ならどこでもOKと考えられます。
ただし、本格的な兜は繊細で丁寧に扱う必要がありますし、直射日光が射し込んだり湿気が多い場所は避けたいところです。
飾り方の基本的な流れとしては、櫃に芯木を置いて袱紗を被せ、鍬形に竜頭といったものを差し込んで芯木に乗せます。
細かな部分が全体の印象を大きく左右する
後は離れて見たり近づいて見て、全体的なバランスを調整します。
細かな部分が全体の印象を大きく左右するので、納得するまでバランスを調整したいものです。
刀や弓といった付属品については、正面を見て右に刀、左に弓を置くのが正解です。
弓が左側、つまり右手側なのは使わずに済む平和を意味するからで、当然ながら刀は鞘に収めた状態で飾ります。
刀は柄が下になるように置くこと、これも間違えやすいので確認と注意が必要です。
兜を含む鎧飾りは、本格的なものは最低でも10万円、上を見れば50万円以上するものもあります。
一方、兜飾りは5万円からが最低ラインですが、上は高くても30万円くらいに収まります。
近年は人形もセットの鎧着大将飾りが注目を集めており、こちらは10万円から20万円が目安です。
コンパクトに収納できる収納飾りは10万円前後が相場で、ケース入りは割と手頃な3万円くらいから選べます。
兜飾りを購入するポイント
兜飾りは子供が成長する度に出して飾るので、飾りやすさや収納のしやすさも含めて、購入を検討することが大事です。
見た目や格好良さだけで選んでしまうと、飾りたくてもスペースがなくて飾れないということになりかねないです。
それと、家族が増えて家族構成が変わったり、将来的に引越ししないとも限らないので、そういう可能性も含めて検討すべきです。
本格的なもので確かな品ならいくら出しても惜しくない、そう考えるなら専門店に相談するのがベストです。
有名な専門店なら品揃えに間違いはありませんし、品質やサポート面にも期待できます。
安さや手軽さを重視すると量販店ですが、専門知識にはあまり期待できないので、商品ごとの違いを確認して選ぶのには不向きです。
品揃えもそれなりだったり、場合によっては取り寄せということにもなりますから、商品を見て購入を検討したいならやはり専門店がおすすめです。
まとめ
量販店はそれほど本格的ではなく、限られた予算でも手頃に購入できる商品を選ぶのに向いています。
結局のところ、兜飾りは大きさや価格に品質など、現実的な部分を見て購入を検討することになるでしょう。
店頭ではデザインや高級感に惹かれることもありますが、価格を見て驚くことも珍しくないです。
職人が細部に至るまで拘り、丁寧に仕上げた商品は作品と言っても過言ではないので、相応の価格がつけられるのは当然です。
最終更新日 2025年6月27日 by uyhom