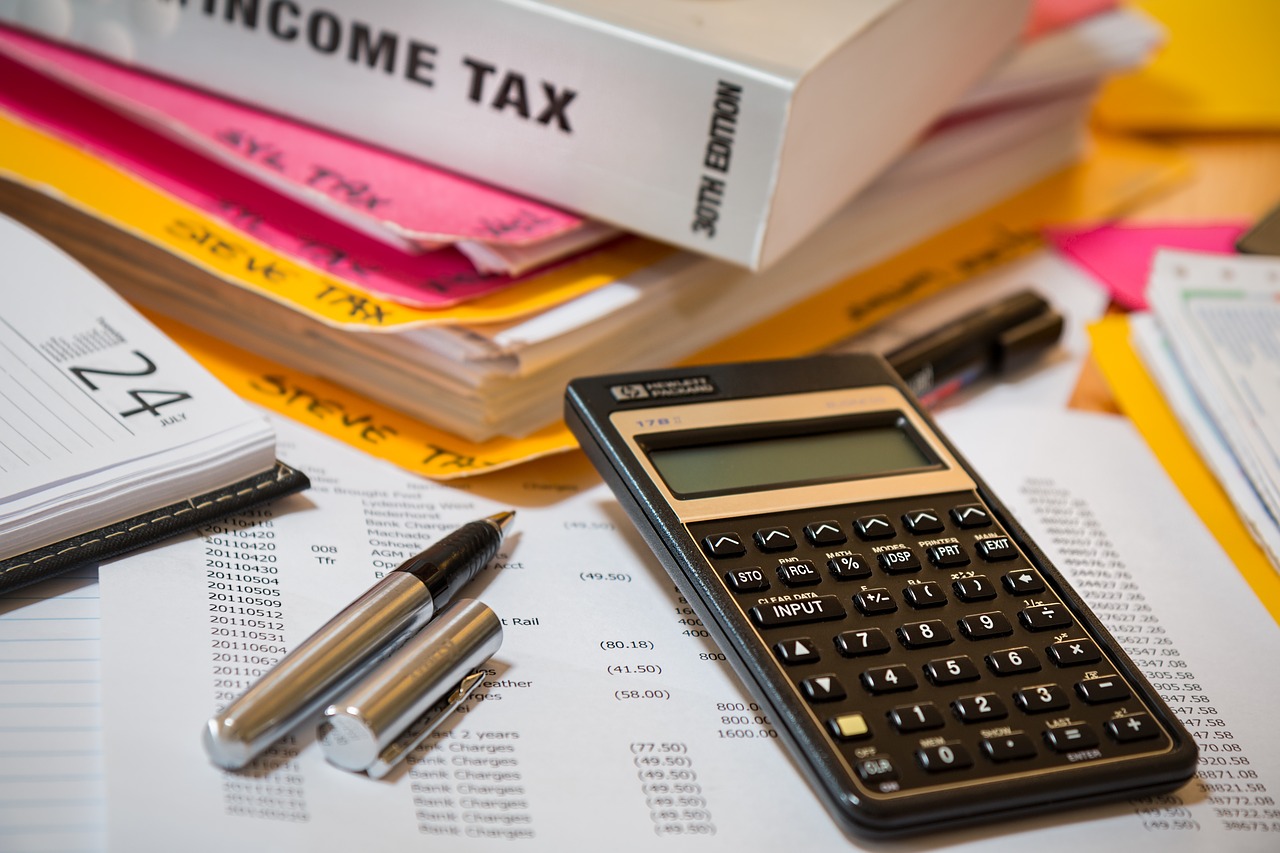税理士法人について
税理士法人とは、複雑化や多様化している納税者などの業務の依頼を税理士が円滑に対応し、安定して高い信頼性を確保できるように平成13年に制度化されたものです。
それまでは個人で行われていましたが、1人で対応するのが困難であるため複数の税理士で行う法人の形態でも認められるようになりました。
業務に関しては税理士に関するものや、定款で定めていればそれに付随している会計業務などを行えます。
法人を設立するためには届出が必要です。
これは成立に日から2週間以内に行うように定められており、その後に変更が発生した場合には遅滞せずにその申請を行います。
なお、新規に設立する際に変更したい場合には届出と同時に変更の申請をすれば良いです。
登記を行うことで成立し、事務所の所在地がある弁理士会の会員になると法令で定められています。
税理士法人と似ているものに税理士事務所がありますが、共通点もありますが運営形態が異なっているものです。
法人化する場合には2人以上の税理士が設立する形式になるため会社という形態になり、税金も法人税が課せられます。
これに対して事務所の場合は個人業務となるので1人で行うことも可能であり、税金は所得税です。
業務の内容はいずれも税理士が行う税務に関する対応などで違いはありません。
法人の場合は定款に具体的に業務を定めておく必要があり、これにより一般人がどこまで対応しているのか明確に理解することができます。
ただし、定款に記載していればどのような事業でも行えるというものではなく、制度によって指定されている範囲のものに限られており、さらに社員は税理士に限定されています。
法人の場合、業務を定めておく必要がある
業務が制限されているのは、そもそも税理士が円滑に対応できるようにするために成立したものであるため、それと関係のないものも扱えるようにするのは適切ではないと考えられるからです。
法人でも扱うことが妥当であると判断されれば、今後は範囲が拡大されることも考えられます。
このような制度ができた背景には個人事業では様々な問題があったからです。
例えば特定の業務に精通する資格を持っている従業員が1人しかおらず、病気や事故で入院した場合などに対応できなくなります。
また、税理士である事業主が死亡した場合には事務所がなくなります。
しかし、日本クレアス税理士法人のような税理士法人であればこのような場合でも税理士は残っており、法人組織であるため業務の継続が可能です。
多くの社員が集まっているのであれば、開業した地域以外にも支店を開くこともできるなどの違いもあります。
そのため規模の大きなものもあり、一見するとより複雑な業務を行っていように思えますが、内容自体は法令で定められているので違いはありません。
個人で行えることと、法人の制度がまだ新しいものであることから、数が多いのは税理士事務所の方であり、税理士法人は全体の1割程度です。
このような状況であることから、多くの支店の展開を行ってブランド化すれば一般に対する周知が可能になり、利用者の増加を見込めるのがメリットになります。
節税効果が高いのも特徴
また、前述したように税金の扱いが異なり、個人では利益が上がるほど税率も高くなる所得税になるのに対し、法人税は基本的に一律になり、経費として計上できる範囲も広くなるので節税効果も高いです。
退職金の支給も可能ですが、これも経費にできます。
欠損金の繰り上げに関しても法人では9年であり、個人の3年と比べて大幅に長くなっています。
税金面では収益が低いときには大きなメリットにはならないため、安定して高い収益を得られるようになったときに法人化の検討をすると良いでしょう。
メリットがある反面、法人は責任に関しては無限になるので誰と設立するのか十分に検討して決定しなければ後悔する場合もあるので注意が必要です。
経営方針が変わるなどすれば手続きが必要になって書類作成が発生したり、意志の統一ができなければ解散も視野にいれなければならなくなるので、長期的に業務を共に行っていける相手を見つけることが重要です。
社会保険の加入が義務になるので負担は増えますが、求人の際には有利になるのでメリットともデメリットとも言えます。
利用者の立場で考えた場合にはどちらであっても取り扱っている業務は同じになるので、立地や金額、周囲の評判などからどちらを選べば良いのか決めれば良いです。
複数の税理士が所属して運営されているのでノウハウなどは法人の方が高い傾向があると言えますが、正式に依頼する前に訪問して自分に合うか調べてみると安心です。
自分が勤務するのであれば、事務所の方が少人数の経営になるので意思決定が速かったり、代表者によっては雰囲気が良いなど働きやすい環境のことがあります。
しかし、全体で5人以下であれば社会保険の加入が任意になるため、加入が義務付けられている法人の方が安心できるとも言えるので、自分がどちらを重視するかで判断すると良いです。
最終更新日 2025年6月27日 by uyhom